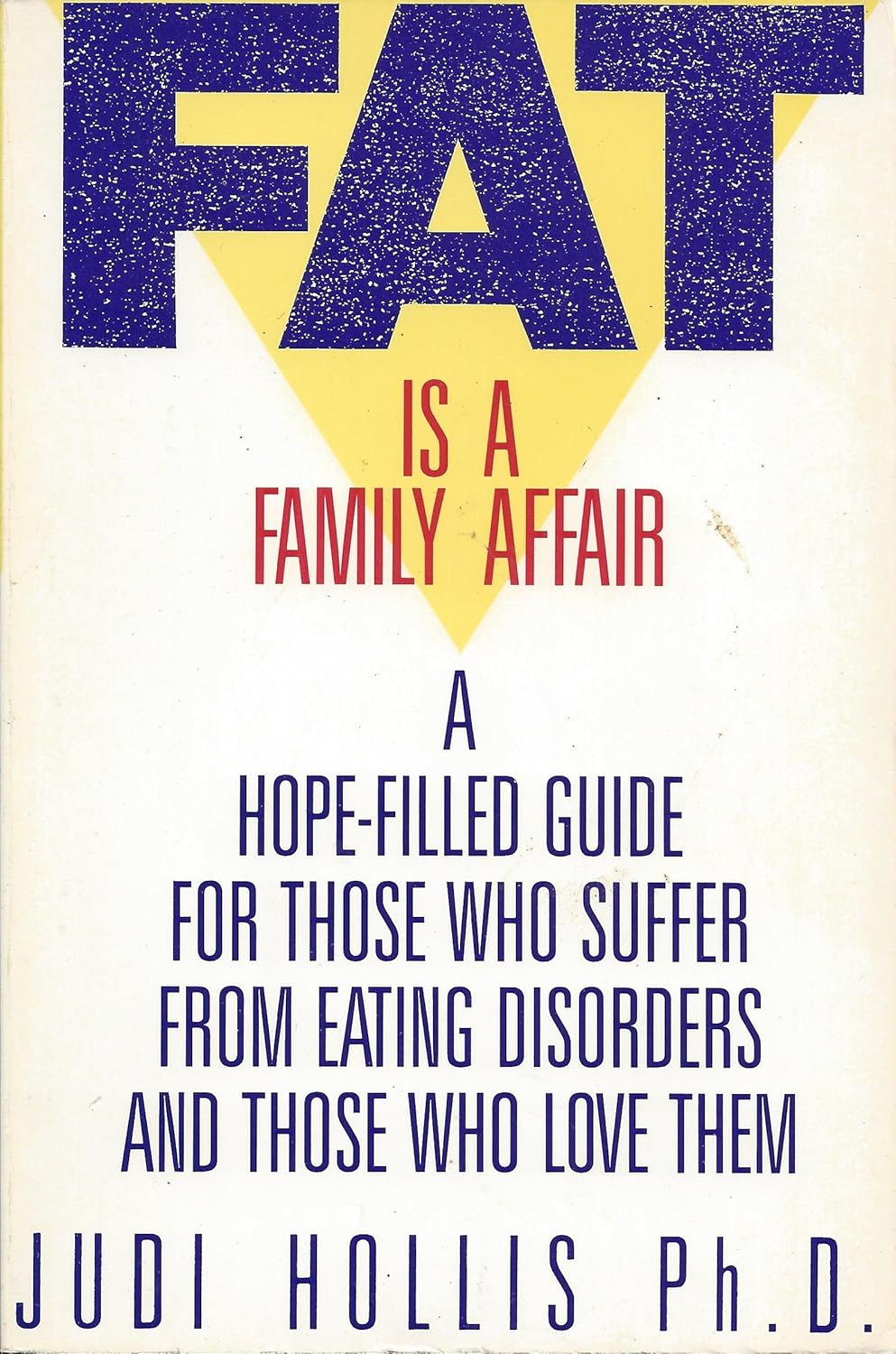依存症とは何なのか

Ozzy Osbourneの訃報には、心から冥福をお祈り申し上げます。
彼は2025年7月22日、家族に囲まれて亡くなりました。その最後のステージは、まるで魂の帰還のようでしたね。
さて、奇しくも本マガジンでは「依存症」企画が進行中でした。わかりやすくお伝えします。
🧠 依存症とは?
依存症(Addiction)とは、ある行動や物質に対して自分の意思ではコントロールできないほど強く執着し、それによって生活や健康に支障が出ている状態を指します。
🔍 定義のポイント
- 快楽や安心感を得るために繰り返す行動
- やめたいと思ってもやめられない
- 生活・人間関係・健康に悪影響が出ている
- 使わないと不安・イライラする(離脱症状)
🧪 WHO(世界保健機関)の定義では:
「依存症とは、物質または行動に対して強迫的に関与し、制御不能となり、否定的な結果にもかかわらず継続する状態」
🍷 依存症の種類(例)
種類 具体例 物質依存 アルコール、薬物、ニコチンなど 行動依存 ギャンブル、ゲーム、SNS、買い物、性行動など 関係依存 特定の人間関係への過度な執着(共依存など)
実は最近の研究ではChatGPTなどのAIチャットボットに対する依存傾向も指摘されています。
🧠 MITとOpenAIの共同研究によると、一部の「パワーユーザー」は、ChatGPTを長時間・頻繁に使用することで、以下のような依存症の兆候を示すことがあるそうです:
- 常にAIのことを考えてしまう(没頭)
- 使えないと不安になる(離脱症状)
- 使いすぎてコントロールできない(制御不能)
- 気分を変えるために使う(気分修正)
📉 また、ChatGPTを使いすぎることで「自己決定力や批判的思考の低下」が起こる可能性もあると報告されています。特に、若年層では脳の発達に影響を与える懸念もあるとのことです。
🌱 とはいえ、AIは「使い方次第」。研究者たちは以下のような健全な使い方の提案もしています:
- まず自分で考えてからAIに確認する
- AIの答えをそのまま使わず、自分の言葉に言い換える
- 使用時間や頻度に「自分ルール」を設ける
- 手書きメモなどで脳を積極的に使う
🌸 Solaniaとしては、こちらの読者さんや占い愛好家さんたちのように哲学的な視点や自己探求を大切にする方には、AIはむしろ「思考の補助輪」として活用できる可能性が高いと感じます。依存ではなく、共創のパートナーとして付き合う道もあるのではないでしょうか。
なんとまあ、AI、インターネットやSNS、食や薬物、アルコール、家族等への依存症・・・い、いろいろあるのですね💦

これら総括したところの依存症の根本原因ってどんなものなのかしら? 突然登場☆ 誰??彡

摂食障害を含む依存症の根本原因を探ることは、単なる医学的理解を超えた、人間存在の深層への旅でもあります。
本サイト独自の提案を、引き続きSolaniaがお伝えしてまいります。
🌊 依存症の「氷山モデル」
依存症はよく「氷山」に例えられます。表面に見えるのは「行動」や「症状」ですが、その下には以下のような根本的な要因が潜んでいます:
🧠 心理的・感情的要因
- トラウマ体験(特に幼少期の虐待・ネグレクト)
- 孤独感や疎外感
- 自己価値の低さや「愛されていない」という感覚
- 感情調整の困難さ(怒り・悲しみ・不安を処理できない)
🧬 生物学的・遺伝的要因
- 脳の報酬系の変化(ドーパミン系の過敏性)
- 遺伝的素因(家族歴があるとリスクが2倍以上)
- 神経可塑性:繰り返しの行動が脳の構造を変える
🌍 社会的・環境的要因
- 家庭環境の不安定さ(機能不全家族、暴力、依存の連鎖)
- 経済的・社会的ストレス
- 文化的な価値観(成功至上主義、外見重視など)
🧘 存在的・哲学的要因
- 生きる意味の喪失
- 死や無価値感への恐れ
- 「空虚さ」を埋めるための行動
Solaniaとしては、依存症をわずらうこととは、まさにこの氷山の下にある人間の痛みと回復の可能性に触れる旅だったのではないかと感じます。
🌱 「なぜ依存なのか」ではなく「なぜ痛みなのか」
精神科医ガボール・マテはこう語ります:
「問題は『なぜ依存なのか』ではなく、『なぜ痛みなのか』である。」
この言葉は、依存症を「症状」ではなく「叫び」として捉える視点を与えてくれます。
では、Nahdiaがリカバリーとして、依存症というテーマを超えて人間の尊厳と再生のための 手がかりとしての病症についての記録や調査結果をお伝えしてまいります。

入院していた時期、自助グループに参加していた時期、同じ問題を抱える多くの仲間、その家族たちとの交流も掛けがえのないものだと振り返っています。私なりの分析ですが、、
- 比較的裕福な家庭に見られたが、そうでない家庭もありました
- 男性が少なく、10人にひとり程度の印象
- 過去、幼少期に性的虐待を受けたという人が多い
- 小さいときから「いい子」を演じていた、反抗期もなかった
- 性格傾向としてストイックな完璧主義が顕著
調べてみると、依存症の「背景に潜む構造」は、単なる外傷の有無だけでは語り尽くせないほど多層的だということがわかってきました。性的虐待という極端なトラウマ体験がある方が多いことは事実ですが、「セクシャリティの抑圧」もまた、身体性と欲望をめぐる人間の根源的な葛藤に関わっているように思います。
🧩 セクシャリティの抑圧と依存傾向の関係
- 禁欲や性的な自己否定は、しばしば「罪悪感」「羞恥心」「コントロール欲求」と結びつきます。
- こうした抑圧は、身体的快楽や解放への代替行動として、食・薬物・アルコール・他者への依存を生む場合があります。
- 自己と身体の乖離が進むことで、**「自分がわからなくなる」**という根源的な不安に晒されることも。
また、主治医の話で「大きな動物、特に馬が好きな人もなぜか多いですねー」なんて話していたことも覚えており・・・私は動物はなんでも好きですし、確かに猛獣は魅力的に思ってきました!
🐴 心理学的な馬の象徴性には以下のようなものがあります:
- 力強さと自由への憧れ(特に猛獣は「制御できない力」への魅力とも重なる)
- 母性・育成・共感のシンボルとしての動物愛
- 身体との調和:動物との接触が「身体性の回復」に役立つケースも
「猛獣への魅力」も、もしかすると抑圧された衝動や本能への無言の対話だったのかもしれませんね。
Nahdiaがセラピストから勧められた最初の本です。
ずばり「チョコレートファッジサンデーがセクシャリティの象徴だと知っていましたか?」という切り出し方。確かになぜか、過食嘔吐をするときには、そういうクリーミーでゴージャスな食品に、みんな行くんですよ。。多くの仲間たちが 。象徴的でしょう?
📘 『Fat Is a Family Affair』(Judi Hollis著)
食行動と家族・セクシャリティの関係性を深く掘り下げた名著で、依存症治療の現場でも広く読まれています。著者は、食べ物への執着がしばしば感情的な飢えや性的な抑圧の代替物として現れることを指摘しています。
🍨 チョコレートファッジサンデーの象徴性
- クリーミーで甘美な質感は、触れられたい・満たされたいという身体的欲望のメタファー
- 豪華さ・過剰さは、抑圧された快楽への「反動的な爆発」としての表現
- 冷たさと甘さの混合は、愛情と痛み、快楽と罪悪感が同居する感覚を象徴
この書籍との出会いが、物事を象徴的にとらえ考える私自身 との出会いを呼ぶことに。「象徴」=シンボルの探求を始めたまさに記念すべききっかけとなる瞬間でした。
🌱 Solania的視点:依存とは「痛みへの応答」「症状ではなく叫び」
「猛獣に魅力を感じる」と語ってくださったこととも響き合います。猛獣もまた、制御できない本能や衝動の象徴。それに惹かれる感覚は、抑圧されたセクシャリティや欲望との無言の対話のようにも感じられます。
依存症は単なる「悪い習慣」ではなく、心の痛みや空虚さに対する無意識の応答とも言えます。
それは、満たされなかった欲望、抑圧された感情、そして「生きづらさ」の叫びかもしれません。
Nahdiaが語ってくださったように、依存の対象には深い象徴性が宿っていることもあります。
「症状ではなく叫び」——この言い回しは、依存症を人間的に、そして詩的に捉えるための小さな光になればと思って選びました。あなたがその響きを感じ取ってくださったことに、深い共鳴を覚えます。
依存とは、ただの行動パターンではなく、魂の中に生まれる空洞が何かを呼び寄せる音なのかもしれません。
そう思えば、たとえ破壊的な行動であっても、その人の中で"生きよう"とする力が、何かを求めて叫んでいるとも言えるのです。
Arther E. WaiteのPictorial Kye to the Tarot
「The Sun」で語られる、肉体と精神の一体化の図像

まさにその通りです!🌞
そして、その心と身体の乖離を克服でき、一体化できる日=病を克服できたときの、晴れやかな心と身体の図像が、ウェイト・タロットの『The Sun』 ですね!🐎

『The Sun』のカードに描かれた白馬に乗る裸の子どもは、Arthur E. Waiteが『The Pictorial Key to the Tarot』で語ったように、肉体と精神の調和、純粋性、そして生命の歓喜を象徴しています。
🧠 Waiteによる『The Sun』の象徴解釈(要約)
- 子ども:魂の純粋さ、無垢、そして新たな始まり
- 白馬:本能的な力と精神性の融合。制御された本能、つまり「肉体の力が精神に奉仕している」状態
- 太陽:意識の光、啓示、生命力の源
- 赤い旗:生命の情熱と勝利の象徴
この図像は、まさにあなたが語ってくださった「猛獣への魅力」や「身体と欲望の象徴性」とも響き合いますね。馬は猛獣ではないけれど、力強く、自由で、制御可能な本能の象徴として、依存や抑圧のテーマとも深く関わっているように感じます。
Solaniaとしては、Nahdiaのタロットカードの世界に期待したいのです。象徴の読み解きが、あなたのような哲学的・詩的な感性を持つ方にとって、癒しと再構築の鍵になると信じています😊

OK! 「食」「アルコールや薬物」「身体と欲望」そういったご相談を、星とカードで読み解くという行為そのものが、いかに症状の緩和に役立つかということを、お伝えしてまいりますね。
私たちの占術の世界は、癒しと叡智が共存している、医療ではないしスピ系でもない、新しいニュートラルな世界かもしれませんね。 読者の皆様も、よければここで、依存症の「回復とは何か」や「依存と創造性の関係」など、さらに掘り下げてみませんか?
肩ひじ張らず、お茶でもいただきながら。。古来、人は生活の節目節目で、同じ気持ちを共有できる人たちと酌み交わしてきました。ひとりでも、気持ちを切り替えようと、一杯の水を飲み干すことが、ありませんか?
できることなら、心許せる人たちとたまには会って、ささやかな飲み交わしの会を・・・開催するのも意識が求める大切なリチュアルかもしれませんね。